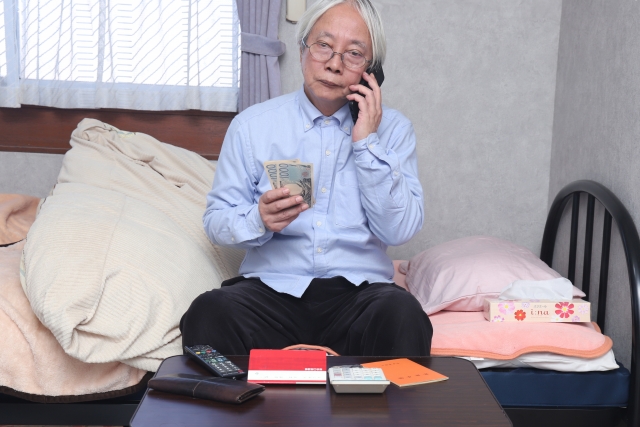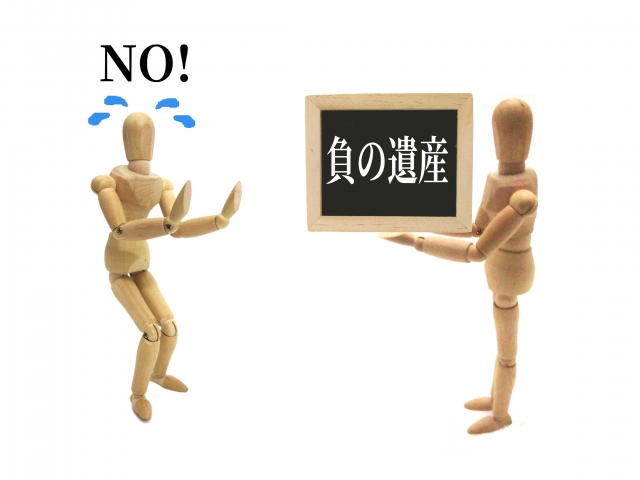最近では少子高齢化社会が進み、子供達が都会に出て定住して帰郷しない。そもそも結婚をしてなくて自分の代で家系が終わってしまうなどの理由で、先祖からの受け継がれたお墓を管理する人が居なくなってしまう事態が多くなっています。旧盆で里帰りされた際に「墓じまい」についてご相談をお受けしたケースも有りました。私自身も数年前に墓じまいの手続きを行った経験があります。今回は「墓じまい手続き」についてお話させて頂きます。
1.関係者への相談
お墓の承継者が一人で決めてしまわず、親族や関係者に事前に相談して理解を得ておくことが大切です。墓じまいは、故人を供養するお墓をなくすことなので、感情的なしこりを残さないためにも丁寧な話し合いや説明を心がけましょう。
2.墓じまいの準備
まず、墓じまい後の供養方法を決めます。永代供養墓(合祀墓):血縁に関わらず、他の方の遺骨と一緒に埋葬される共同のお墓です。費用を抑えたい方や、お墓参りの負担を減らしたい方に向いています。樹木葬:墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓です。自然志向の方に人気があります。納骨堂:屋内の施設で、個別のロッカーなどに遺骨を安置します。天候に左右されずお参りできます。手元供養:自宅で遺骨を保管し、供養する方法です。散骨:遺骨を海や山などに撒く方法です。新しい供養先が決まったら、墓地管理者へ墓じまいの意向を伝えます。使用許可証や管理費の支払い状況などを確認しておきましょう。
3.改葬手続き
遺骨を新しい場所に移すことを「改葬」といいます。改葬には、市区町村から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。改葬許可証取得までの流れですが
現在の墓地がある市区町村役場で、「改葬許可申請書」を取得します。墓地管理者に「埋蔵証明書」を発行してもらいます。新しい供養先の管理者に「受入証明書」を発行してもらいます。申請書に必要事項を記入し、埋蔵証明書と受入証明書を添えて、市区町村役場へ提出します。
4.墓石の撤去・閉眼供養
改葬許可証が発行されたら、いよいよ墓石の撤去です。事前に、石材店に見積もりを依頼しておきましょう。費用は墓地の広さや、作業の難易度によって異なります。墓じまいをする際は、寺院の僧侶に「閉眼供養(魂抜き)」を依頼するのが一般的です。閉眼供養とは、墓石から故人の魂を抜き、単なる石に戻すための儀式です。
5.遺骨の取り出しと新しい供養先への埋葬
閉眼供養後、石材店が墓石を撤去し、遺骨を取り出します。取り出した遺骨は、新しい供養先へ移し、納骨・埋葬します。
墓じまいの費用
墓じまいにかかる費用は、以下の3つが主な内訳です。閉眼供養のお布施や檀家を離れることになる離檀料:寺院へのお礼です。墓石の解体・撤去費用:石材店に支払う費用です。(寺院が業者を指定している場合もあります。)新しい供養先への費用:永代供養料や納骨費用などです。これらの費用は、選択する供養方法や墓地の立地などによって大きく変動します。合計で50万円〜200万円程度が相場とされています。(あくまでもケースバイケースです。)
墓じまいは時間と手間がかかります。法的な根拠はありませんが、檀家を離れることになる場合の離檀料などで話し合い上手く進まないケースも見受けられます。行政手続きなども、思いがけず手間がかかったり、スムーズに運ばない事もあります。先ずは分からないことは、行政書士などの専門家に相談されることをお勧め致します。
「行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士 宅地建物取引士 辻賢一