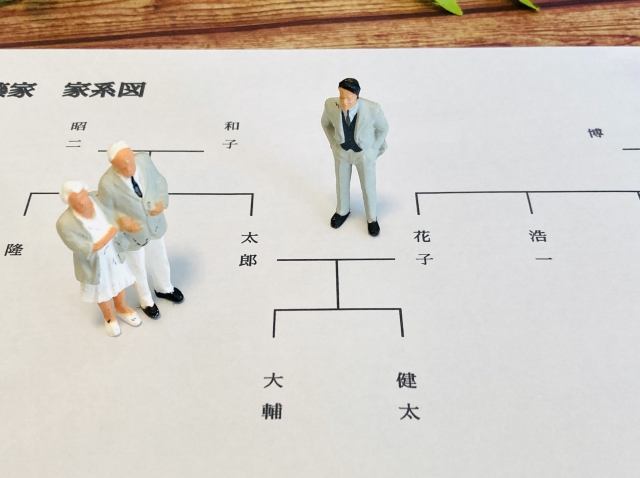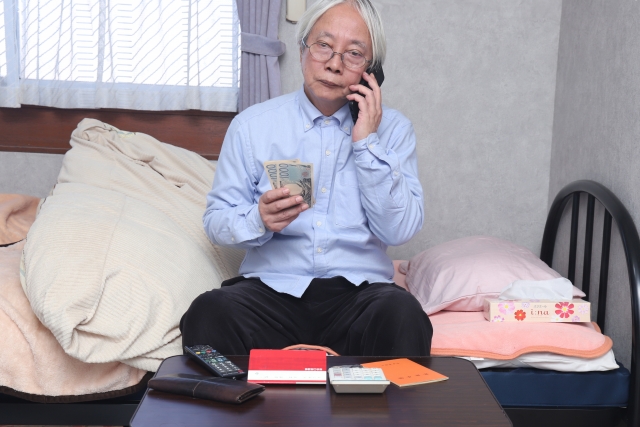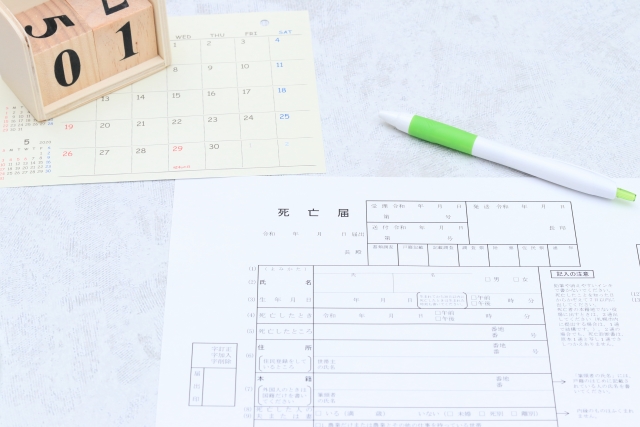なるべく分かりやすく、短くまとめてみました。
「生前贈与」と相続税の改正
2024年の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間(相続前何年前の贈与までを課税対象になるのか)が「3年から7年」に長くなりました。これにより、節税対策(年間で基礎控除額110万円)としての生前贈与が見直されています。
課題として:節税対策を考えている方は早めの資産移転が必要になります。
関心を持たれている世代:高齢の資産家(被相続人)やその子ども世代(相続人)の方。
「デジタル財産」の取り扱い
問題点として:暗号資産(仮想通貨)、ネット銀行口座、SNSアカウントなどのデジタル資産の相続が新たな問題になりつつあります。
困ることとして:相続人がデジタル財産の存在を把握できない。(紙ベースの通帳が無い。)IDやパスワードが分からなくて、アクセス出来ないなど。
対策として:エンディングノートや遺言での明記が重要ですし、日頃の家族間の話し合いの場を持つなどコミュニケーションが大切になります。
家族信託(民事信託)の活用
高齢化の進展と認知症リスクの増加により、財産管理や相続対策としての家族信託の利用が今注目されています。任意後見制度や法定後見制度は分かりにくい運用しづらいとの指摘もあります。
利点として:成年後見制度より柔軟に資産を管理できる。
関心を持たれている世代:親(被相続人)の介護・財産管理を担う子世代(相続人)の方。
空き家・地方の不動産の相続問題
問題点として:相続した家や土地が地方や過疎地にある場合は価値が少なく売れない処分できない「負動産(ふどうさん)」と化して相続放棄される例が増えています。空き家になり、荒れ果てて近隣住民に環境面で迷惑になるなどの相続を放棄後の維持管理が問題になっています。
バックボーンとして:維持費や固定資産税が重荷なっている。
注目の政策として:2023年の「相続土地国庫帰属制度」の活用が注目されています。
相続登記の義務化
注目点として:不動産相続後の登記が義務化され、正当な理由がないのに登記しないと過料(最大10万円)が科されるようになりました。
法整備の目的として:所有者不明土地の増加を防ぐ。(空家問題)震災等が起きた後の再開発事業が土地の所有者不明や相続登記がされていなかった為に手続きが遅れて進まなかったことなどが挙げられます。
影響のある人達として:過去に相続して登記していない人も対象となります。
関連する社会的バックボーンとして少子高齢化や単身高齢者の増加が挙げられます。以前にお話させて頂いた老老相続問題など相続トラブルによる家庭崩壊のリスクも起きています。相続問題での疑問点、お困りごとや悩み事は、先ずは街の身近な相談者であるお近くの行政書士事務所にご相談下さい。
「行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士 マンション管理士 宅地建物取引士 辻賢一